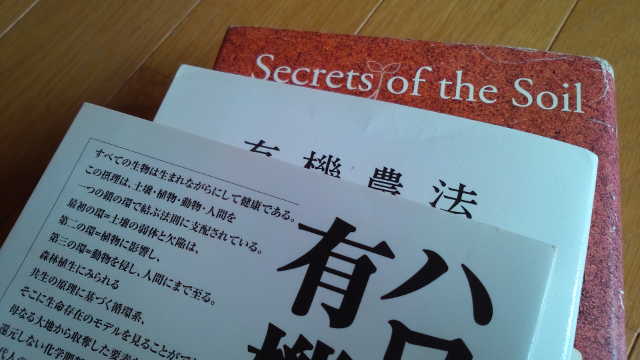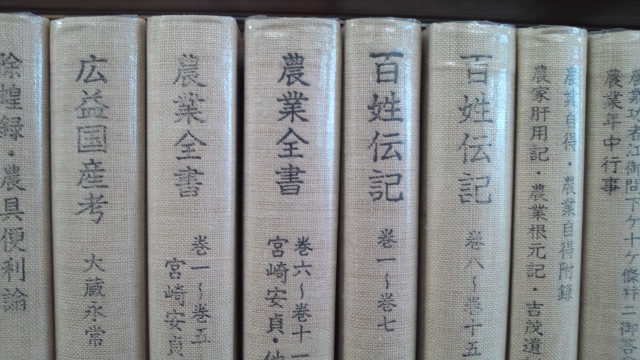やっぱりいいですね、シロカラシは綺麗で
春カラシ(商品名)は検索するとシロカラシと全く同じに見えるので、きっとホワイトマスタードの緑肥用品種なんだと思います。
小麦の前作休閑緑肥としての栽培なので、収穫はせずに肥料として鋤き込みます。

約2週間くらい綺麗な花を楽しめます。
この黄色い花畑の明るい黄色と独特な花粉の香りの影響力は結構大きくて、辺り一帯の雰囲気を変えてしまいます。
この間も畑の隅にどこかの車が止まってましたので、きっと写真でも撮っていたんだと思います。
畑を肥やしつつ人の心を癒すなんて素晴らしいですね。